囲碁の上達に欠かせないのが「詰碁」。
多くのプロ棋士が、囲碁上達の勉強法としておすすめしています。
本コラムでは、詰碁を解くことで得られる効果をはじめ、効果的なやり方や取り組むコツ、初心者から高段者までのレベル別の勉強法を解説します。
詰碁を解くとどのような効果があるのか知りたい、詰碁が大事なのは分かっているがどのように勉強すればいいか分からない、という方はぜひ最後までご覧ください。
詰碁の効果とは?
詰碁の主な効果は以下の3つです。
- 手筋が身につく
- ヨミの力がつく
- 死活に強くなる
手筋が身につく
詰碁を繰り返し解くことで、様々な手筋が身につきます。
詰碁は手筋の宝庫です。
手筋は実戦で打てれば勝敗を左右することがあるほど強力ですが、知らないとなかなか打てない手も多いです。
そのため、コツコツ勉強して知識として身につけていくことが重要です。
身についた手筋は、実戦で石の生き死にが問題となる局面はもちろん、中盤の戦いや終盤のヨセなど、一局を通して効果を発揮します。
ヨミの力がつく
詰碁はヨミの力をつけるのにも適しています。
対局中は、もちろん実際に石を置いて考えることはできません。
そのため、頭の中だけで考える力が求められます。
最初は考えている途中で頭の中の石が消えてしまったり、どこに石があるか分からなくなったりしてしまうかもしれません。
しかし、繰り返し詰碁に取り組むことで、徐々に頭の中のイメージが鮮明になっていくでしょう。
死活に強くなる
詰碁には、死活に強くなるという効果もあります。
数多くの詰碁を解いていくと、死活の感覚が磨かれていきます。
死活に強くなると、「この石はもう生きているから他の場所に回ろう」「相手の石が薄い形をしているから何か良い手がありそう」といったような判断ができるようになるでしょう。
逆に、死活に弱いと「生きていると思っていたのに死んでしまった」ということが起こります。
石の生き死には、それだけで一局を左右するほど勝敗への影響があります。
せっかくの好局を落とさないためにも、苦しい形勢から一発逆転するためにも、死活に強くなることは重要です。
詰碁の効果的なやり方
詰碁の効果的なやり方としておすすめしたいのは、以下の流れです。
- しっかり考える
- 答えを確認する
- 問題図に戻って復習する
もちろんアプリで詰碁を解くのも効果がありますが、ここでは本での勉強を想定して解説していきます。
しっかり考える
まずは問題図を見て、自分なりにしっかり考えましょう。
注意したいのは、自分に都合のよい手だけを考えないことです。
相手が常に最強の手を打ってくることを想定していなければ、いくら先の手を考えてもヨミとは言えません。
ヨミ切って答えが分かったと確信したら、答えを確認します。
どうしても分からない場合は、無理せず次のステップに進みましょう。
答えを見て確認する
次に答えを見て、正解図を確認します。
この際、自分の答えが合っていたかどうかだけではなく、失敗図や変化図などもチェックしましょう。
正解しても、考えていなかった変化や失敗図から手筋を学べることもあります。
一通り掲載されている図を確認して終わりではなく、最後のステップに進みます。
問題図に戻って復習する
ここが一番重要です。
正解図や失敗図を確認したらもう一度問題図に戻り、頭の中で碁石を並べて復習しましょう。
間違えた問題はもちろんですが、正解した問題もしっかり復習することで、一つの問題からより多くの効果が期待できます。
面倒くさいと思われるかもしれませんが、こうした地道な確認が、実戦で役に立つヨミの力を鍛えるために重要です。
以上、3つのステップを意識しながら詰碁を解くと、より一層効果的な勉強になるでしょう。
ポイント:分からなかったら答えを見ても大丈夫
考えても分からない問題は、思い切って答えを見てしまうことも大事です。
正解図や失敗図を確認し、手筋を学び、問題図に戻って復習すれば十分意味のある勉強になります。
「詰碁が解けるまで答えを見てはいけない」という人もいれば、「分からなかったらさっさと答えを見てどんどん筋を学ぶべき」という人もいます。
専門家の中でも意見が分かれるところで難しい問題です。
一概にどちらが正しいと言えることではなく、自分に合ったやり方で取り組むのがよいでしょう。
しかし、分かるまで答えを見ないようにすると詰碁を解くのが苦痛になり、嫌になってしまうかもしれません。
そのため、はじめのうちは、考えても分からなかったら答えを見て、どんどん詰碁にチャレンジすることをおすすめします。
詰碁のコツ
詰碁を楽しく継続するコツは以下の3つです。
- 簡単な問題から徐々にレベルアップする
- 無理のない範囲で続ける
- 同じ問題集を繰り返し解く
簡単な問題から徐々にレベルアップする
まず重要なのが、簡単な問題から徐々にレベルアップするということです。
ありがちな失敗パターンは、
いきなり難しい問題にチャレンジする→解けなくてやる気がなくなる→詰碁が嫌いになる
という流れです。
おすすめは、自分の棋力から2ランクくらい下の簡単な問題集です。
例えば、上級者なら二桁級、有段者なら級位者くらいの問題集から始めてみるとよいでしょう。
しかし、詰碁の対象棋力というのは問題の作者によってもバラバラです。
級位者向けの問題が、別の本では有段者向けとして紹介されている、ということもあります。
そのため棋力に関してはあまり神経質にならず、あくまで参考程度に考えるのがおすすめです。
もし簡単な問題集を選んで解き始めたはずなのに難しく感じた場合は、思い切ってさらに簡単な問題集に取り組みましょう。
無理のない範囲で続ける
無理のない範囲で続けるというのも重要です。
上達のためには、毎日少しでも囲碁に触れる時間を作るのが理想です。
しかし囲碁を一局打つのは、時間や体力が必要なので続けるのは大変でしょう。
その点、詰碁なら手軽に取り組めます。
毎日詰碁に挑戦することで、手筋やヨミの力がメキメキ身につきます。
継続のコツは、一日のノルマをできるだけ簡単にすることです。
「毎日5分詰碁の時間をつくる」「1日1問だけ詰碁を解く」など、これならできそうと思えるものにしましょう。
余裕があったら、プラスしてもう少し詰碁を頑張ってみる、という程度の気構えの方が継続しやすいです。
続けること自体を目的にするくらいの気持ちで始めてみましょう。
同じ問題集を繰り返し解く
一度解いたら終わりではなく、同じ問題集を繰り返し解くようにすると効果的です。
すべての問題をノータイムで解けるようになればベストです。
詰碁の問題は、理解度によって大きく3種類に分類できます。
- 考えても分からない
- 考えたら解ける
- 見た瞬間に答えが分かる
「考えても分からない」問題は実戦で出てきても解けないので、まずは問題集で解けるようにしましょう。
問題集を解いていて「考えたら解ける」と思っても、これだけではまだ不十分です。
実戦で活かすためには、「見た瞬間に答えが分かる」レベルまでもっていくことが必要です。
その理由は2つあります。
1つは、実際の対局では、多くの場合時間制限があるからです。
問題集のようにじっくり考えるヒマがないことが多く、瞬時に答えを導けないと実戦で活かすことは難しいでしょう。
もう1つは、問題集は「問題であること自体」がヒントになっているからです。
実戦では「この石は黒から打つと取ることができます」と教えてくれることはありません。
そのため、「考えたら解ける」段階の問題では、実戦に出てきたとしても気が付かない可能性すらあります。
考えるのではなく反射的に答えが分かる状態を目指して、繰り返し問題集を解いてみましょう。
レベル別の詰碁勉強法
ここでは詰碁の勉強法を、初心者から高段者まで4つのレベルに分けてご紹介します。
初心者
初心者の方は、まず眼と欠け目の違いを意識し、しっかり理解するところから始めましょう。
その後は1手で解ける基本的な問題に取り組みます。
石の配置や問題の向きが変わっても正解できるまで、繰り返しチャレンジしてみましょう。
級位者
初心者を脱したら、実戦に頻出の基本手筋を身につけるフェーズに入ります。
手数の少ないシンプルな問題を中心に、数多くの問題を解くのがおすすめです。
分からなかったら答えを見て、新しい知識をどんどん吸収していきましょう。
有段者
有段者になったら、少し高度な問題を解いてみましょう。
「基本死活」と呼ばれる実戦形の勉強を始めるのも効果的。
基本的な形は、見ただけで生き死にを判断できるようになることを目指しましょう。
高段者
高段者の方は、基本手筋を組み合わせた複雑な問題もしっかり解けるようになる必要があります。
一部の難解なものを除き、基本死活も一通りマスターしましょう。
さらに上を目指すなら、古典詰碁などの難解なものを解いて、高度な手筋や長手数のヨミが求められる問題にも挑戦していきましょう。
詰碁で囲碁の地力をつけよう!
詰碁は囲碁上達の王道トレーニングです。
地道ですが、コツコツ続けることで手筋やヨミの力といった地力がつき、確実に棋力の向上に役立ちます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、自分のレベルにあった問題から少しずつ取り組めば大丈夫。
毎日1問でも構いません。
小さな積み重ねが、確かな上達につながります。
ぜひ今日から詰碁にチャレンジしてみてください。
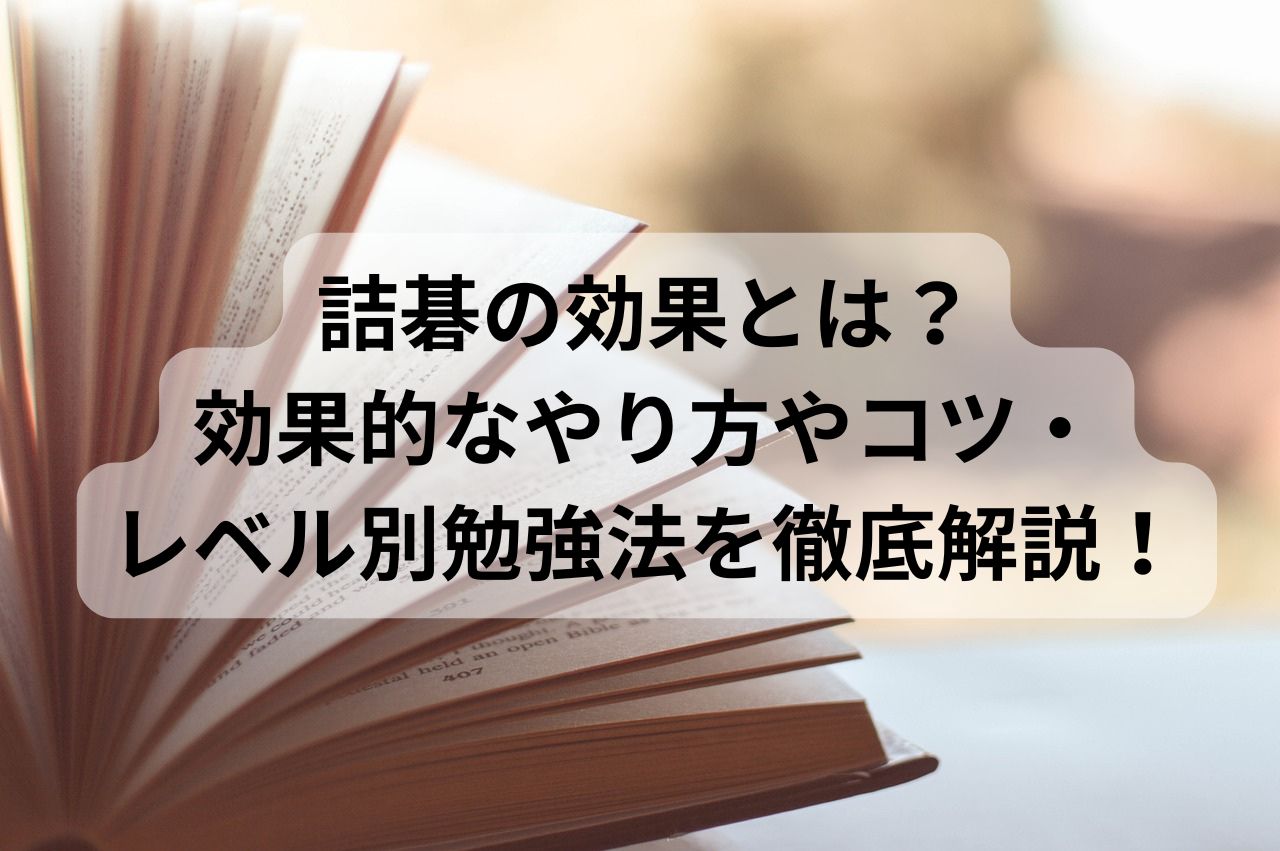

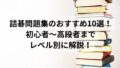
コメント