囲碁が強くなりたいと思ったとき、あなたはどんな勉強法を思い浮かべますか?
詰碁を解く、実戦をたくさん打つ、プロの対局を観戦する。
その中でも、昔から多くの人に支持されてきた学習法が「棋譜並べ」です。
「ただ石を並べるだけで本当に上達するの?」
そう思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、棋譜並べは囲碁の上達において欠かせない勉強法です。
この記事では、
- そもそも棋譜とは何か?
- 棋譜並べの効果とは?
- 上達につながる効果的なやり方
についてわかりやすく解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
囲碁の棋譜並べとは何か?基礎からわかりやすく解説
囲碁を勉強していると「棋譜並べ」という言葉をよく耳にするかと思います。
これは、プロの棋士や強い人の対局の記録(=棋譜)を見ながら、その手順通りに石を並べて再現していく学習法です。
はじめて聞くと「ただ並べるだけで上達するの?」と思うかもしれませんが、プロアマ問わず多くの人が「棋譜並べ」を通して囲碁の感覚を養ってきました。
ここでは、まず「棋譜」とは何か、そして「棋譜並べ」がどんな練習法なのか、なぜ効果があるのかをわかりやすく解説していきます。
そもそも「棋譜」とは?
「棋譜(きふ)」とは、囲碁の対局で打たれた一手一手を記録したものです。
たとえば、ある対局で「黒が右上の星に打った」「白が左下にカカった」といった情報を、順番に番号をつけて記録していきます。
最近では紙ではなく、スマホやパソコンのアプリで保存されていることも多いです。
つまり棋譜並べをして対局のを再現することで、プロや上級者の手の流れを体験できるわけです。
「棋譜並べ」とはどういう勉強方法?
「棋譜並べ」は、その棋譜を見ながら盤上に石を一手ずつ並べていく学習方法です。
やり方はとてもシンプルで、黒1・白2・黒3…と順番通りに石を置いていくだけ。
ですが、並べながら「なぜこの手を打ったんだろう?」「自分ならどうするかな?」と考えることで、強い人の思考や判断基準に近づいていくことができます。
初めのうちは意味がわからなくても大丈夫です。
何度も繰り返していくうちに、「この形はよく出てくるな」「なんとなく自分ならここに打ちたい」など、囲碁のセンスや感覚が少しずつ身についていきます。
なぜ囲碁の勉強で棋譜並べが重視されるのか
棋譜並べは、単なる「手順の再現」ではありません。
囲碁が上達するために必要な「読み」「形」「感覚」「大局観」などを一気に学べる総合トレーニングです。
具体的には次のような力が養われます。
- プロの打ち方や思考パターンが自然と身につく
- 定石や布石、ヨセなど、局面ごとの考え方がわかるようになる
- 自分の打ち方と比較しながら、強くなるヒントが得られる
さらに、何度も繰り返して並べることで、石の配置が記憶に残りやすくなり、実戦で迷わず打てる場面が増えていきます。
一見地味に思われるかもしれませんが、非常に効果的な勉強法なのです。
棋譜並べの効果とは?囲碁が強くなる理由
囲碁を学ぶうえで、「棋譜並べ」はとても地味に見えるかもしれません。
ですが実は、詰碁や実戦と並んで、多くの上級者が取り入れている王道の勉強法です。
なぜこれほどまでに重要視されているのか?
それは、棋譜並べが囲碁に必要な力を総合的に伸ばしてくれるからです。
以下では、具体的にどんな力が身につくのかを解説していきます。
プロの打ち方を体感できる
プロの対局には、無駄のない手順、美しい形、そして深い読みがあります。
棋譜並べをすることで、プロの流れるような手順を、自分の感覚として体にしみこませることができます。
最初は理由がわからなくても、「この形、よく見るな」「このあたりで方向転換してる」といった気づきが自然と増えていきます。
コツコツ続けることで、自然と自分の打ち方や考え方に良い影響を与えてくれるでしょう。
読みの力が身につく
「読みの力」といえば詰碁というイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし棋譜並べでも読みの力を鍛えることは可能です。
棋譜をただ並べるだけでなく、「次はどこに打つのか」「それに対してどう応じるのか」と考えながら進めることで、次の一手を考える力=“読み”の力が鍛えられます。
実戦でも、数手先を読む力があるかどうかで結果が大きく変わりますよね。
棋譜並べは、プロの正確な手順に触れながら、「どうしてこの手を選んだのか?」という思考を追体験できるので、読みの練習としてとても効果的です。
定石や布石の理解が深まる
棋譜並べを繰り返していると、定石(序盤の形)や布石(盤面全体の構想)が自然と身につきます。
書籍で学ぶ定石だけでは「この形は知ってるけど、その後がわからない」ということがよくあります。
でも、棋譜並べでは実際の対局の中でその定石がどう使われ、どう展開されるのかを体感できます。
「定石通りに進まなかったとき、プロはどう打っているのか?」
そんなリアルな判断の積み重ねが、あなたの定石理解を何倍にも深めてくれるはずです。
大局観・形成判断力が向上する
棋譜並べを続けていると、「この打ち方は全体に厚いな」「こっちに展開したいな」など、盤面全体を見る力=大局観が少しずつ育っていきます。
また、「この時点で黒が良さそう」「ここで白が苦しそう」といった形勢判断力も自然と養われていきます。
特に上級者から有段者、高段者を目指したい方は、部分的な技術だけでなく「全体の流れを読む力」が重要になります。
棋譜並べは、そんな大局的な視野を身につけるための、まさに最適なトレーニングと言えるでしょう。
効果的な棋譜並べのやり方とは?
棋譜並べはただの“手順の再現”ではなく、やり方次第で上達スピードが大きく変わる学習法です。
ここでは、特に効果が高い3つのコツをご紹介します。
同じ棋譜を何度も並べる
「一度並べたからもう終わり」と思っていませんか?
実は、同じ棋譜を繰り返し並べることこそ、上達への近道です。
最初は意味がわからなかった手も、2回目・3回目と繰り返すうちに盤面全体を見る余裕ができ、「このあたりで流れが変わったな」「この一手がポイントだったのかも」と気づけるようになります。
また、繰り返し並べることで形や感覚が身体に染み込み、囲碁の地力がつくことでしょう。
好きな棋士を見つける
棋譜並べを継続するには、「誰の対局を並べるか」がとても大事です。
おすすめは、打ち方や考え方に共感できる「推し棋士」を見つけることです。
たとえば、
- じっくり厚みを作って中終盤で競り勝つ人
- 実利重視で先行逃げ切り型の人
- 戦いが好きで乱戦に強い人
といった視点で、「自分の理想像」に近い棋士を見つけてみてください。
その棋士の棋譜を何局も並べることで、自分のスタイルも自然とその方向に磨かれていきます。
何より、「好きな棋士の碁に触れる時間」は、勉強でありながらも楽しい時間になるはずです。
自分ならどう打つか考えながら並べる
少し上級者向けですが、ただ棋譜を並べるだけでなく「自分だったらここでどう打つか?」と一手ごとに考えながら並べると、学習効果が一気に高まります。
ただ順番通りに石を置いていくだけでは、手順を「追う」ことはできても、「理解する」ことはなかなかできません。
そこでおすすめなのが、「次の一手を考えてから棋譜を確認する」という方法です。
この方法を続けていくと、
- 実戦でも冷静に手を選べるようになる
- 自分の癖や弱点に気づける
- 読みや判断の質が高まる
といった効果が期待できるでしょう。
棋譜並べに慣れてきたなと感じたら、ぜひ取り入れてみてください。
棋譜並べで楽しく棋力向上を目指そう
棋譜並べは、囲碁の実力をじっくりと底上げしてくれる、非常に効果的な学習法です。
プロの手をなぞり、その考えを感じ、自分の感覚として取り込んでいきましょう。
その積み重ねが、読みや形、大局観といった囲碁に必要な力を育ててくれます。
さらに、好きな棋士の碁を並べたり、自分で一手ずつ考えたりすることで、学びながらも楽しさを感じられるのが棋譜並べの魅力です。
ぜひ囲碁の勉強に少しずつ棋譜並べを取り入れ、楽しみながら強くなりましょう。

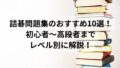

コメント